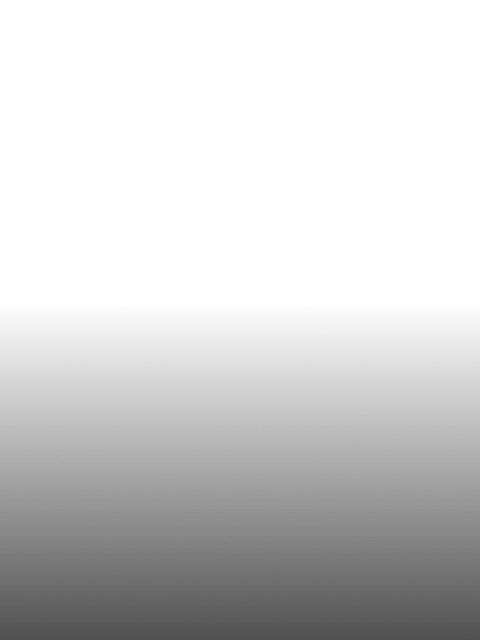利用条件
- チャンネルの購読はのに限られます
- チャンネルの購読はに限られます
- チャンネルの購読はに限られます
- チャンネルの購読はに限られます
- チャンネルの閲覧には新しい働き方会議へのアカウント登録/ログインが必要です
注意事項
- 購読ライセンスの期限を超えると、チャンネルを閲覧できません。購読ライセンスを新たにご購入ください
- 一度ご購入された購読ライセンスの返金はできません
これまでのご利用、誠にありがとうございました。
(サイト紹介文) 会社を解雇されたり,給料が支払われなかったりするなど,会社(事業主)と個々の従業員との労働関係に関するトラブルを個別労働紛争といいます。個別労働紛争を解決する手続には,裁判所や労働局,弁護士会など複数の機関に様々なものがありますが,各手続にはそれぞれ特徴があり,紛争の実情等を踏まえてど の手続を利用するのが良いのかを検討することが大切です。 (コメント) 以下のPDFに、労働紛争解決の簡便な方法である、①地方裁判所における労働審判手続,②簡易裁判所における少額訴訟手続や③民事調停手続について、具体的な内容や手続が記載されています。 特に簡易裁判所の少額訴訟と民事調停については、弁護士に依頼せず自分一人でも手続可能なものとして紹介されています。 http://www.courts.go.jp/vcms_lf/H26.12kouhou2.pdf


今回のGUEST 山口絵理子氏 マザーハウス代表取締役社長 兼 デザイナー アジア最貧国の1つ、バングラデシュ発の高品質のバッグを製造・販売するマザーハウス。設立は2006年。東京都台東区入谷の1店舗からスタートし、2013年現在、国内12店舗、台湾4店舗で展開し、バングラデシュの工場も合わせると、国を超えた約200人の組織に成長した。 同社は、高級ブランド店がウィンドーを並べる大手百貨店にも出店している。出店当初は苦戦したものの、スタッフ一人ひとりが来店客の声を聞き、試行錯誤して工夫を重ね、いつしかトップに立った。 バングラデシュの製造工場でも、毎夜、ベンガル人たちが侃々諤々の議論を重ねる。「ここがダメ」「もっとこうすべき」と。それが功を奏して、設立当初はほとんどの商品にダメ出しをしていたが、今や現地人による検品がほぼ可能なレベルまでこぎつけた。 熱くて結びつきが強く、高い成果を生み出す「チーム」がここにある。なぜ、このようなチームになりえたのか。日本ラグビーフットボール協会・中竹竜二氏が、同社代表取締役社長・山口絵理子氏に聞いた。 山口絵理子氏 Yamaguchi Eriko_慶應義塾大学総合政策学部在学中、米国ワシントン・米州開発銀行でインターンを経験。政府の開発支援に違和感を抱き、バングラデシュへ。バングラデシュBRAC大学院開発学部修士課程に入学後、日本の商社にてダッカ事務所でインターンとして働く。ジュート(麻の一種)という素材と出合い、2006年にマザーハウスを設立、バッグなどの製造・販売を開始。「フジサンケイ女性起業家支援プロジェクト2006」最優秀賞受賞。「Young Global Leaders 2008」選出。著書に『裸でも生きる――25歳女性起業家の号泣戦記』『裸でも生きる2 Keep Walking私は歩き続ける』『自分思考』(以上、講談社)がある。 ■ 計画性なく出発した会社が、今や200人を超えた 中竹 マザーハウスの成長の軌跡を見ていると、最初から組織をどれくらいまで大きくして、こういう人を採用して、と計画していたわけではないようです。気づいたら、周りに人が集まっていたというのが正しいですよね。 山口 設立当初は、家族がメンバーでしたからほんの数人です。計画性はまったくなかったのですが、事業を走らせるうちに、国内70人、バングラデシュで110人、台湾で25人と、約200人の組織になっていました。 中竹 「マネジメント」という意識がまったくなかったということですが、それはある意味、貴重なリーダーシップです。なぜこんなふうに人が集まって、200人の組織になったのでしょうか。「途上国から世界に通用するブランドをつくる」というビジョンが人を結びつけているのでしょうか。 山口 確かに、このビジョンには私の経験や思いが詰まっています。バングラデシュに渡り、そこで厳しい現実を目の当たりにしました。組織力を持たない自分に変えられることは、ほんの小さなことでした。それでも、現地の素材と技術を使った高品質のプロダクトをつくることによって、付加価値の高いものを求めて訪れる人が増え、途上国に経済構造の変化が起きる日が来れば――そう願って設立したのがマザーハウスです。この私の思いを、強くメンバーたちにも発信しています。 でも、会社のみんなが、途上国に対して私と同じくらい思いが強いかというとそうではありません。たとえば、副社長の山崎大祐は、この会社が本気で社会を変えられると信じて大企業を辞めてうちに来てくれました。そして、新しいことに挑戦したくて入社した人もいます。そういうふうに志向は違っていても、「何のために働いているのか」は根底でつながっています。社会に対して、自分らしい強みや方法で何らかの貢献をしたいという人が集まっているのだと思います。 ■ どんなにキャリアがあっても「現場」からスタート 中竹 でも、マザーハウスにはメディアを見て、単なる憧れで入ってくる人もいるでしょう。そういう人たちをどうやって見極めているんですか。 山口 最初は、ほとんど「憧れ」という人が多いです(笑)。でも、拒否するのではなく、きちんと理解してもらおうと思っています。入社後は例えばまず、倉庫で検品してもらったり、店舗での経験を重視しています。私たちはあくまで小売り。1個1個、商品をきちんと見てもらって、クオリティの高いものをどうやってつくるのかを知ってもらいます。 そして、どんなにキャリアがあっても、「現場」つまりお店からのスタートです。事務所勤務も、駐在員も、どんな仕事でもまず、お店で店長を目指してもらいます。「社会に貢献する」ことは大事ですが、頭でっかちではダメ。小売りは現場で売ってこその事業ですから。お給料もお店で働くスタッフがいちばんもらえる仕組みにしています。 ■ 突きつけられた「社員が辞めるのは社長の責任」という現実 中竹 「現場第一」という一貫性があるからこそ、順調に組織が大きくなっていったんですね。 山口 いえ、決して順調なときばかりではなかったんです。起業して2年目、3年目のころ、次々と人が辞めていきました。そのとき、ある社員から、「あなたが社長だから人が辞めていくんです」と書かれた手紙をもらって……。「うまくいかないのは、社長である私の責任」だと、客観的に突きつけられたのです。それまでは、会社を軌道に乗せることに必死で周囲が何も見えていませんでした。 中竹 そのとき、どうしたんですか? 山口 スタッフみんなに、私のいやなところをノートに書いてもらいました。そしたら、出てくる、出てくる(笑)。それまでは私が頑張れるんだから、みんなも同じように頑張れると思っていました。でも、アフターファイブを大事にしたい人など、自分以外の価値観を持つ人がいることを実感したんです。私の価値観を押し付けるのではなく、それぞれの価値観を認めなければ人が楽しく働けない、と。そのノートは今も家に取ってあります。 中竹 多くのリーダーは、部下に「あなたのせいだ」と言われても無視したり、相手が悪いと受け流したりします。「自分の悪いところを書いて」とは言えません。 山口 もともとは「こうあるべき」というプライドがないからでしょう。大きな企業で働いた経験がありませんから、「社長」がどんな存在か知らなかったんです。だから起こったことに対して、真摯に向き合って、手探りで自分のあり方を見つけていくしかありませんでした。 ■「自分にできるのはほんの1%」という気づき 中竹 そうやっていくうちに、マネジメントが楽しくなってきましたか。 山口 ぜんぜん(笑)。どうにかしてマネジメントに携わる時間を縮めたいと思っていました。人それぞれの価値観は認めてはいましたが、やはりどこかで自分が走れば走るほど会社が大きくなると考えていました。 でも、今はようやく楽しくなりました。その理由は、人が育ってきたからです。信頼できる人に任せれば、基本的にうまくいくんです。 中竹 マネジメントがつらかったときの自分に何か言うとしたら? 山口 自分にできるのはほんの1%。残りほとんどはみんなの力がなければ成し遂げられないということに、早く気付け、ということでしょうか。自分でやったほうが3倍速いし、質も高い。でも、時間がないから、仕方なく任せている――そんなひどい人間でした。それが間違いだとわかったのは、人が育って、お店のことは店舗統括に、生産効率のことは工場長に聞いたほうがずっとよく知っているし、うまく対処してくれるとわかったから。だったら自分が出ないほうがいいと、心からそう思えました。 ■「正解」を知らないから、全員で学びながら走る! 中竹 山口さんは、いつも走りながら失敗して、学んで、それを活かして、ということを繰り返しています。 山口 さっきも言いましたが、私はビジネスにおける「正解」を知らずに起業しました。それがよかったのかもしれません。私と同じ時期に起業して、残念ながらうまくいかなかった人たちには理想とする正解があって、そこまで届かないから、自分はダメだ、自分の会社もダメだと結論付ける。 私たちにはいつも目標はあるけれど、そこに初めは届かなくて当たり前、と思っています。なぜ届かないか考えて、できるだけ早く軌道修正をして。その繰り返しで、私たちなりの「正解」にたどり着いて、事業を拡大してきました。百貨店で最初は成績が悪くても、どんどん売り上げが上がっていくのは、スタッフ全員がお客さまを見て、軌道修正しているからでしょうね。 中竹 会社全体として学ぶ姿勢を持っているのがすごい。トップである山口さんの姿勢が、伝播しているのかもしれません。 山口 全員が、自分たちは何も知らないと思っているから、みんなで学び合って、学んだことを共有して。私たちも発展途上なのです。 中竹 ほかの会社には、自分たちは何でも知っていると思っている人たちもいます。 山口 確かに、大企業から転職してきた社員にはそういう人もいて、うまくいかない場合があります。あくまで、私たちは新しいことをやっている、モデルがないからやってみなければわからない、というスタンスを保てるかどうかが重要です。 ■ バングラデシュの工場でも、自発的に夜遅くまで「振り返り」 中竹 それは、海外でも同じですか。 山口 たとえばバングラデシュの工場はすごいですね。出荷後のミーティングは特に、ベンガル語でワーワー(笑)。「ここの作業が甘かった」とか、「ここのプロセスが遅い」とか。終業時間は20時ですが、22時になることも。それが今、毎日になってしまって、経営者としては困っているくらいです。彼らは確かに失敗するんですが、そこで振り返ってみて、ただでは起きない、何か拾ってから次にいこう、という精神がそこにあります。 中竹 国を超えても、同じ精神を持つチームとして機能しているんですね。 山口 そこは、「見える化」の力かもしれません。いいものをつくって、出荷すれば評価される。それが実感できない工場が、世の中の99%ではないでしょうか。いくつかのテーブルに分かれて作業するんですが、それぞれのテーブルがどれだけ頑張ったかグラフ化しています。振り返りと学び、そして評価をしっかりつなげているんです。 中竹 目の前で頑張っていること。毎日、振り返って学ぶこと。それが品質の向上につながっていると心から実感しているんですね。 山口 最初は不良品が本当に多かったんですよ。そこで、どうすれば不良品を減らす努力をしてくれるのかを考えました。結論は、「誰かが喜ぶ」ということを理解してもらうこと。だからエイチ・アイ・エスに企画を持ち込んで、お客さまをバングラデシュの工場にご案内するツアーを企画したんです。工場に大型バスが着いて、30人のお客さまが自社工場にやって来る。そこで初めて、「多くの日本人がiPhoneを使っているからポケットのサイズを変えよう」といった意見が工場から出るようになりましたし、お客さまに自社の製品が愛されていることを知って、振り返りと改善にかける時間が長くなったんです。また、このツアーは、「添乗員」として同行する日本のスタッフが現場をより深く知る機会にもなっているんですよ。 ■ビジョンと自分、現場と自分とのつながりが見えれば、人は変わる 中竹 海外と日本。目の前で頑張っていることとお客さまの喜ぶ顔、そして自分への評価。ビジョンと商品。「点」で存在するバラバラなものをつなげることが、経営者の大事な役割かもしれません。それを綿密にやっているところが、マザーハウスの強みです。 山口 確かに、「一直線で見えること」は、当社の強みかもしれません。たとえば、直営店のスタッフたちは、商品の説明だけでなく、バッグができるまでのすべてを語れる「ストーリーテラー」として頑張ってくれています。牛革の製造から、お客さまに購入していただくところまで、全部見える。それをやりがいにつなげなければもったいないと思っています。 中竹 逆に、つながらないとうまくいきませんか。 山口 そうですね。最初はデザインをしてくれる人を探していて、日本にいる方にきれいな絵を描いてもらいました。でもその通りにできることなんて絶対ないのに後から気がついて。結果的にモノを作るってそのプロセスを構築しないといけないんだって気がつきました。 マザーハウスの場合、1人で絵を描く仕事ではなく、工場のみんながデザイナーだと思ってくれるのがゴールなのです。品質は下げられません。いいデザインだとしても、大量のロットを工場で生産する過程で、品質が下がっていくものでは意味がありません。みんなの意見を取り込んで、工場のみんなが自分のアイデアだと思い込んで、一生懸命つくってくれるデザインにする必要があります。だとすれば、デザイナーというより、コミュニケーション業です。すると、自分の強みを活かしていかに貢献するか、という根底の部分がどうしても重要になります。私がデザインしたものをつくって、という、どこか上から目線の態度が見えると、現場の人は付いてきてくれません。 中竹 人材育成の世界では、スキル、知識、経験は教育できますが、態度を変えるのは難しいといわれます。マザーハウスの場合、ビジョンと自分、現場と自分とのつながりを持てないと態度は変わりませんよね。マザーハウスに限らず、優秀な駐在員を送っても、どこか上から目線の態度で、現地でいいチームがつくれないことがあるようです。 ■ 現場に入った瞬間、社長もメンバーも同じ目線の高さに 山口 バングラデシュに進出したのにうまくいかず、撤退する企業が少なくありません。一時はバングラデシュへの進出はブームでしたが、「ベンガル人は扱いにくい」と言って帰ってしまう。本当に向き合ったのか、と思うこともあります。 中竹 ゆとり世代は使えない、といった議論も同じです。目線を同じ高さにして、本気でつながりを持とうとしていません。山口さんの場合、バングラデシュの工場に行くと、誰が社長かわからないと言われるそうですね。 山口 それどころか、私の「職業」を入社して半年の社員に聞いたら、生産管理だと言っていました。別のスタッフは商品開発担当だと(笑)。ハサミを手に、誰よりもたくさん材料の革を切っている。工場に着いて、2時間くらいはリュックを背負ったまま。忘れてしまうんです。 中竹 社長としては組織構造上、強いリーダーシップを発揮しながらも、現場に入った瞬間にはメンバーシップに転換しています。社長であろうが工場スタッフであろうが、ものをつくる現場、売る現場では、全員が同じ目線に立つ「メンバー」という組織のあり方がマザーハウスでは実現されているんですね。 インタビュー後記 マザーハウスに見る 次世代のチーム像 学ぶ姿勢がもたらす、全員参加のメンバーシップ 中竹竜二氏 日本ラグビーフットボール協会 コーチングディレクター ■ 「フォロワーシップ」から「メンバーシップ」へ バブル崩壊以降の失われた20年からの回復を成し遂げるため、近年まで強いカリスマリーダーが求められていました。現場の強さが、高い経済成長を導いてきた日本にはそれがなじまない。当時から私はそう考え、優秀なフォロワーが組織のゴールに向かって自律的に動き、リーダーがそれを支える「フォロワーシップ」型組織の重要性を唱えました。 しかし、本来的に私が浸透すべきと思っているのは、リーダーとフォロワーのどちらが強い・弱い、どちらが上・下ということではなく、全員が同じ目線の高さで自らの強みを発揮し、ゴールを目指す「メンバーシップ型」の組織です。リーダーシップ型の組織を志向する日本企業に、「メンバーシップ」といってもなかなか理解できるとは思えず、リーダーシップの対極にある「フォロワーシップ」にまずはシフトしてほしいと考えました。 その瞬間、最も強みを活かすべき人が一歩前に出る フォロワーシップの重要性は、「自律型人材」という言葉とともに徐々に浸透してきたと思います。ここでいよいよ、私たちが志向するのは、メンバーシップ型の組織です。メンバーシップ型の組織は、役職名やポジションにかかわらず、全員が組織の目標に責任を持ち、自分がそのときどき、できることを考え、行動に移します。ときにはリーダーがフォロワーとなり、また、ときにはフォロワーの1人が組織を引っ張ります。明日、何が起こるかわからない。そんなめまぐるしい変化のなかで、さまざまな状況に対応するにあたって、誰の強みがそのとき最も輝くのかはわかりません。ですから、上下関係があることに意味がないのです。次世代型組織の1つの解は、メンバーシップが機能する組織なのです。 マザーハウスの現場は、まさにメンバーシップ型の組織といっていいでしょう。工場や売り場では全員が「メンバー」であり、上下関係はありません。社長である山口氏を含めた全員が、同じ目線の高さで現場に真摯に向き合っています。なぜ、このような組織ができたのでしょうか。 ■ 遠くの現場で起こっている問題でも、社員全員が「解」を探す まず、山口氏が、最初から戦略を決め、それを実行してきた経営者ではないということ。山口氏は、誰よりも「自分たちは新しいことをやっているのだから、正解はない」ということを知っています。自ら現場の真っただ中に入り、自ら課題を発見し、学んで、軌道修正をすることによって成果を挙げてきました。 そして今や、山口氏の「学び」の高速回転に、全員を巻き込んでいます。山口氏は、「正解はない」ことを前提に、現場で起こっていることと、社員一人ひとりの仕事というバラバラの「点」を、「牛革の製造から店舗でお客さまに手渡しするところまで」、国やポジションを超え、すべて見える化する努力によって「線」でつなぎました。 日本で商品が売れない。バングラデシュの工場で不良品率が高まった。たとえばこのような遠くの現場で起こっていることでも、今、このときの「正解」を全員が探そうとします。「まだ見ぬ新しい何か」を達成するために、山口氏と同じように、自ら課題を発見し、学んで、軌道を修正します。今、自分がこの場を引っ張るときなのか、誰かを支えるときなのか、メンバーとして何をなすべきかを考え、その役割を変えてゴールを目指しているのです。 Nakatake Ryuji_1993年早稲田大学人間科学部入学。4年時にラグビー蹴球部の主将を務め、全国大学選手権準優勝。97年卒業後、単身渡英。レスタ―大学大学院社会学修士課程修了。2001年三菱総合研究所入社。2006年早稲田大学ラグビー蹴球部監督に就任。2007年度から2年連続で、全国大学選手権制覇。2010年2月退任。同年4月、日本ラグビーフットボール協会コーチングディレクターに就任し、指導者の育成、一貫指導体制構築に努める。2012年度はラグビーU20日本代表監督を兼任。主な著書に『判断と決断』(東洋経済新報社)、『人を育てる期待のかけ方』(ディスカヴァー・トゥエンティワ ン)、『リーダーシップからフォロワーシップへ』(阪急コミュニケーションズ)、『挫折と挑戦』(PHP研究所)、『部下を育てるリーダーのレトリック』(日経BP社)など多数。日本におけるフォロワーシップ論の提唱者の1人。 *元記事は以下のリンクから読めます。 http://www.works-i.com/publication/works/works-web-special/nextage/山口絵理子氏(マザーハウス)