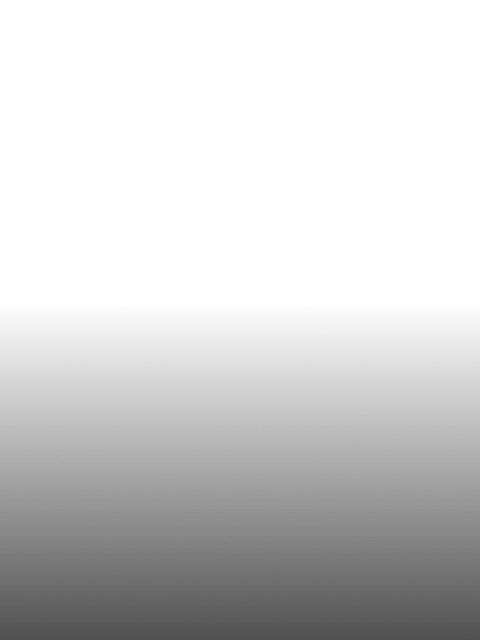利用条件
- チャンネルの購読はのに限られます
- チャンネルの購読はに限られます
- チャンネルの購読はに限られます
- チャンネルの購読はに限られます
- チャンネルの閲覧には新しい働き方会議へのアカウント登録/ログインが必要です
注意事項
- 購読ライセンスの期限を超えると、チャンネルを閲覧できません。購読ライセンスを新たにご購入ください
- 一度ご購入された購読ライセンスの返金はできません
これまでのご利用、誠にありがとうございました。

(記事全文) ◇若者の意識調査、7カ国中最低−−中央大教授・山田昌弘 2014年版「子ども・若者白書」が公表された。特集で紹介されたのが、若者の意識調査の国際比較の結果である。日本で将来に希望を持つ若者は61・6%で、調査対象7カ国の中で最低。40歳になった時に自分が幸せになっていると思う人の割合も、66・2%で最低だった。 私が著書「希望格差社会」(ちくま文庫)の中で「今、希望を持てる若者と持てない若者に二極化している」と書いたのが、ちょうど10年前のことだ。その中で、ある米国の社会心理学者の「希望」が生まれる条件「努力が報われると思えば希望が生じ、努力が無駄になると感じれば絶望が生じる」を引用し、「日本では『努力しても報われない』状況に置かれている若者が増えている」と論じた。 その代表的存在が「非正規雇用の若者」である。学校卒業時点で正社員になれなかったり、一度辞めてしまったりすると、努力してもなかなか安定した正社員になれない。多少時給は上がっても、必要なくなれば解雇されてしまう。彼らは夢を見ることはできても、日々の仕事に希望を持つことは難しい。 希望に限らず、「感情」にはその人が置かれた環境が影響する。日本で若者の非正規雇用比率が4割程度であることを考えると、将来に希望を持てない若者の割合はこの数字と重なる。 調査で取り上げられた欧米諸国や韓国は、日本以上に若者の雇用状況は良くない。新卒採用はまれで、若年失業率は日本以上に高い。収入が低く不安定な職に就く若者も多い。それでも彼らは希望を持っている。なぜなら、「今不安定でも、努力すれば安定した職に就くチャンスがある」「失敗してもやり直しがきく」と思えるからである。これらの国では、失業中でも、不本意な仕事に就いていても、将来、いくらでも就職や転職のチャンスがあるからだ。 しかし、日本では人生の早い時期での格差が一生続く。安定した優良企業の正社員、公務員になれた若者は、人並みに努力すれば認められ、昇進し、定年まで安定した生活を送る見通しが持てる。一方、学卒後に正社員就職できなかった者、辞めた者は希望を持ちにくい。アルバイトや派遣、期間工などの非正規雇用者は、その仕事で人並みに努力しても報われる見通しは少ない。報われる仕事に就くためには、正社員以上の能力を付け超人的な努力が必要なのだ。 日本が他の先進国と比べて希望が持てない若者が多いのは、「新卒一括採用の慣行」と「正社員と非正社員の間の大きなギャップ」があり、若い時の格差が固定化してしまうからだ。結局、この10年間、若者が置かれた「希望格差」という状況は全く変わっていない。 ============== ■ことば ◇厳しい若者の雇用状況 「子ども・若者白書」は、特集で日本を含む7カ国の満13〜29歳の若者の意識調査を実施。日本の若者の「職場満足度」は46%で調査国で最低。収入や老後の年金など、働くことに関する全項目で「不安」の回答割合が他国より高かった。厳しい若者の雇用状況が改めて示された。 *元記事は以下のリンクから読めます。 http://mainichi.jp/shimen/news/20140702ddm004070013000c.html
今回のGuest 湯浅 誠氏 社会活動家/法政大学教授 Yuasa Makoto_ホームレス支援活動などを経て、2008年末の年越し派遣村村長に。2009年から足掛け3年にわたり内閣府参与を務める。内閣官房社会的包摂推進室長、震災ボランティア連携室長などを歴任。政策決定の現場で、官民協働と民主主義の成熟の重要性を訴える。2014年より法政大学教授。 年越し派遣村の村長として注目を集めた社会活動家、湯浅誠氏。その後は内閣府の参与に就任するなど、社会問題の現場と行政の両面を知る希有な存在となった。1つの組織にとどまらず、数々のムーブメントを起こす湯浅氏に、中竹竜二氏がそのチームづくりとリーダーシップについて聞いた。 ■ 場づくりに欠かせない“テーマ設定”と“仕掛け” 中竹 湯浅さんはご自身の活動を、一言でどう表現しますか。 湯浅 社会活動家は、一言でいえば場をつくる人。経営者でも部署の課長でも、スポーツチームでも、仲間を増やして場をつくれば活動家です。僕はそのなかで、社会問題に関する場づくりをしているので、社会活動家というわけです。派遣村はもちろん、内閣府参与も立場の違う官僚のなかで仲間をつくって物事を進めるのですから、1つの場づくりでしたね。 中竹 極論すると、世の中のリーダーの目的は利益を挙げる、試合に勝つなど目的はさまざまだけれど、そこで生じる問題を解決するための場づくりをしているという点では共通している、と。ならば、湯浅さんのリーダーシップはすべての組織に当てはまります。場づくりでは、何を意識していますか。 湯浅 試行錯誤ですが、立ち上げ時のポイントの1つはテーマ設定。もう1つは仕掛けです。私がやっていることは、ある種、偏見の強い分野なので、いかに当事者や当事者以外の人に集まってもらうかがとても重要なんです。 中竹 たとえば、そこにすごいプロダクトがある、誰もが会いたいアイドルがいる……そうであれば人はそれに食いついてきます。でも、湯浅さんが取り組んでいる問題は、人の関心を引くのがかなり難しい。それでも関心を呼び、人を集めるそのノウハウは、マーケティングの領域のみならず、社員を仕事に向かわせることにも応用可能ではないでしょうか。 湯浅 1つは、よく見ること。たとえば“貧困”は、人を集めるためのテーマ設定でした。障がい者問題でいえば、権利条約や年金問題の優先順位が高い。ところが実際になかに入って、よく見て、話してみると、働く場所が限定的で低所得者が多く、生活苦がかなり深刻。それでも前面には出てきにくいんです。それは引きこもりなどの問題でも共通しています。異なる問題を“貧困”というテーマ設定でつなげれば、多くの人が集まる場をつくれると思いました。その人がどういうリアリティのなかにいるのかを見ないと、結び目が見えないのです。 ■ 濃厚なコミュニケーションの場を生む“いい炊き出し” 中竹 “つなげる”は、湯浅さんにとってキーワードですね。 湯浅 “つなげる”ことが、場づくりの仕掛けそのものなんです。ホームレス支援を例に取りましょう。私たちはホームレスの人たちのために週1回炊き出しをしていました。それに対して、「週1回くらいやっても、根本的な解決にはならない」という批判がありました。でも、そんなことは私たちもわかっている。炊き出しの目的は「ごはんをあげること」じゃないんです。私たちは炊き出しには“いい炊き出し”と“悪い炊き出し”があると思っていました。 中竹 どういうことですか。 湯浅 “悪い炊き出し”は、運営者側が調理して、ただ渡す。すると、ホームレスの人たちはただ受け取って食べるだけになります。そこには接点が生まれず、関係はあげる人、もらう人に固定化していきます。一方、“いい炊き出し”は、共同炊事。「人手が足りないから手伝ってください」とホームレスのおじさんに言えば、一緒になって調理して、ご飯食べて、片付けて、とやっていると3時間くらい話ができるし、調理の面では彼らから教えられることも多い。そこに違う関係性ができて、コミュニケーションが濃厚な場が生まれる。これが、仕掛けが重要、という意味なんです。 きちんと出会えば、触れて、知って、変わる 中竹 子どもたちをホームレスの人たちの支援に招いていましたね。意図的に呼んでいるんですか。 湯浅 呼びかけていました。中学生くらいになると、偏見を持つようになる。ホームレスの人が襲撃されて、年に1人くらいは亡くなっています。襲撃するのは高校生や若者が多い。そういう、加害者になってしまう若者たちを追っているジャーナリストに話を聴くと、その子たち自身、家に居場所がなくて、外でうさばらしをしている、という構図のようです。そういうことが起こらないように、出会いの場をつくりたかったんです。 中竹 子どもたちを呼ぶのは、それなりに大変ですよね。 湯浅 子どもたちは学校の先生に連れられてでないと来ません。しかも「怖い人なんじゃないか」など、いろんな想像をして来ます。でも、帰るときに必ず彼らはこう言う。「なんだ、普通の人じゃん」と。触れて、知って、変わる。これが大事なのです。 中竹 来てもらうために、どう口説くんですか。 湯浅 私たちが直接対応するのは先生ですが、もう、あの手この手ですよ(笑)。たとえば、私の経験とか。私の兄は障がい者なんです。それがよかったと思っています。私が通っていた学校は、健常者ばかりでした。小さい頃は、自分が通っている学校がすべてですよね。でも、私の場合、兄が障がい者だったので、障がい者のコミュニティとも接点があって、いろんな人がいるなあと、肌で感じていました。私が多様な人、物事に対して抵抗感がないのは、その経験が大きく影響しています。子どもたちにも、早い時期にそういう経験をして欲しい。そんなことを話したりしました。 ■ 思いを持つ個人と組織に必要な「つながりの作法」 中竹 仕掛けといえば、話題になったアイスバケツチャレンジはどうですか。 湯浅 良いと思います。社会の多くの人が今までまったく視界の外にあった問題に関心を持つようになる、という意味では一定の効果があります。ただし、あるレベルを超えると、そのことに批判的な人も含めて調整をしていかなければ物事が動かない。政策や法律、ルールづくりといった領域になると、多様な利害関係者を調整して形にし、維持・運営していくための組織力が必要になります。それを乗り越えられるかが社会活動の大きな課題ですね。 中竹 問題を提起する人を組織力が支援することで、大きなムーブメントになっていく。企業の変革と社会活動は、まったく同じですね。 湯浅 NPOや社会活動は、有機農業のようなものだと私は考えています。有機農業の耕地面積は、日本全体の農地の0.3%にすぎません。でも、同じ100円のキャベツならば、大半の人が、有機農法でつくられたキャベツを買うでしょう。シェアは小さいものの、人々の価値判断基準と行動を変えたんですから、社会的インパクトは大きいですよね。私たちの活動を見ても、NPOが雇用吸収力を持つかというとそうではない。でも、私たちが発信することを問題として政府や企業、個人個人が受け止めてくれたら、そこには大きな意義があります。しかしそれを動かしていくのは、やはり「組織」です。自治体や政府、企業などに働きかけ、協働しなければならない理由はそこでしょう。 中竹 企業の活動になぞらえると、さまざまなプロジェクトや新規事業、アイデアが出てきても、組織側がきちんと受け止めて支援しないと大きなムーブメントになりません。どうしたら、思いを持つ個人と組織がつながることができるのでしょうか。 湯浅 出会いには「作法」があります。それが不幸な出会いになると、「だから組織はだめなんだ」とか、「あいつら、なにやってるんだ」とか、お互いの気持ちがすれ違い、接点が見つけられません。NPOが被災地に行って、住民とトラブルになることがありますが、それもつながりの作法が下手なんだと思います。相手とつながろうと思ったら、相手の領分や役割を認め合うことが重要です。それぞれが「私はここまではやれる」と出し合って、皆がそれぞれ力を出し合っても手の届かない「穴」を見つける。そのうえで、その「穴」をどう埋めようかという話し合いをする。皆が「穴」を埋めるという同じ方角を向いた探求モードになれればベストです。「ここはそっちがやれ」と一方的に言ったり、囲い込みをしたりするようではうまくいきません。 ■ 場の維持のためには「聴く」主体的になってはじめて人は動く 湯浅 組織力のほかに、場を維持・運営していくために重要なことがあります。それは「相手の話を聴くこと」です。 中竹 僕自身、聴くことはチームマネジメントのなかで非常に重要な位置を占めています。湯浅さんの場合、「聴く」ことと「場の維持・運営」にはどんな関わりがあるんですか。 湯浅 私の場合、30代前半まで、人の話をまったく聴きませんでした。私がやりたいからやる。一緒にやりたいならば付いてくればいい。そんな風に考えていたんです。そのとき、私は大学院で研究員の卵でもあったので、社会活動も研究者仲間で議論しているノリでした。そしたら、周りから誰もいなくなって。それではダメだと気づいて、やり方を変えたのです。人の話を聴かずに、ただ強く発信して巻き込むだけだと、周囲の人は「あいつを手伝ってやっている」という意識にしかならず、不満も出やすい。話を聴いても不満は出ますが、こちらの問いかけによって本人の動機が熟していくので、主体的になれます。だから、持続のためには「聴くこと」が何より大事なのです。 中竹 誰もいなくなったとき、普通は違うところに原因を求めるものです。もっといいことを言えば、人は集まってくるのではないか、と思ったりはしなかったんですか。 湯浅 そのとき、どこかで読んだ本に書いてあったことを思い出したんです。現実社会では理論で打ち負かしても恨まれることしかない。物事を一緒にやるには、議論するのとは違うモードが必要。確か、坂本龍馬がそんなことを言っていたと。そういうことかなあと思いました。 中竹 ご自身のスタイルを変えたんですね。 湯浅 はい。考えてみれば、NPOに相談に来る人や、支援を受ける人に対するコミュニケーションと基本は一緒です。相談者に対しても、私が答えを言うのは簡単ですが、その人は私が出した答えの通りには動かない。すると、なんでそう動かないんだとこっちはイライラする。でも、結局は本人の腹に落ちないと、行動にはつながらないんです。 中竹 それはすごく大事なことですね。人はついつい教えたがります。 湯浅 こちらが請け負って問題を解決しても、本人の「生きる力」は増えていませんから。だから結局、問いかけて、考えてもらって、その人の話を聴くことが重要なのです。相談者にはそういう対応をしてきたのに、組織の仲間づくりではそうしていませんでした。それを同じにしただけで、時間はかかりましたが、うまくいくようになりましたね。 ■ 社会に場をつくるというプロフェッショナルリーダー 中竹 この連載のテーマは、次世代のリーダー、次世代のチームのあり方を模索していくことです。湯浅さんは組織のなかのリーダーというより、社会全体という大きなくくりで見たときに、場をつくるリーダーです。こういう人が社会に求められているのではないかと思います。 湯浅 ありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいです。 中竹 かつてリーダーには、「カリスマ性」が求められました。言い換えると、自分にしかできないことを多くつくればつくるほど、組織のなかで絶対的な存在になります。すると、みんなが言うことを聞かざるを得なくなる。すごい人がどんどんすごくなって、それによって上意下達のヒエラルキー型組織ができていきました。ところが最近は逆です。リーダーは、人にどんどん仕事を任せて、自分の仕事を少なくしていく。フォロワーたちの力に恃(たの)むことで、組織を成長させていく、というのが最近のリーダーシップ論の主流です。それでも、その思想には、1つの組織内で完結したリーダーシップという発想しかありません。湯浅さんの場合は、組織をどんどんつくって、どんどん離れて、またつくって、を繰り返す。ビジネスでもそういうやり方をする「プロフェッショナルリーダー」が出てきたら、組織が活性化するのではないかと思います。プロジェクトをつくって、仕事をしたら次の組織へ。そんな働き方も今後は一般的になりかもしれません。組織人になるのはいやだけど、場づくりで貢献できるという人はたくさんいますから。 ■ “場は質より量” 場が足りないと行き詰まる 湯浅 私自身は場をつくったら、なるべく早く人に譲って次に行きたいんですね(笑)。何か1つやると、そのなかから次はこういうことが必要なんじゃないか、といろいろ思いついてしまう。私は、“場は質より量”だと思っていまして。日本には圧倒的に“居場所”が足りない。1カ所しか居場所がないとほかに行けないから、こじれてもしがみつこうとして面倒なことになる。Aが合わなければB、Bが合わなければCと、もっと転々とできるぐらい場があったら、苦しむ人が減るはずなんです。 中竹 選択肢が多いことは、安心材料になります。 湯浅 ですから、量をまず増やそうと。50人全員にとっての理想的な場はつくれません。大事なのは、ここじゃないと思った人が、次に行ける社会です。 中竹 スポーツの世界でも同じです。日本では、スポーツは部活が中心。チームが合わず、退部、退会すると、その競技自体もやめざるを得なくなります。一方、海外では地域に多くのクラブチームがあり、あるチームに合わなければ別のチームに行けばよくて、競技は継続できる。場があり、そこに行き来があることは、人を育てる、人が育つという意味でも重要だと思います。 インタビュアー 中竹竜二氏 日本ラグビーフットボール協会 コーチングディレクター 湯浅さんは、問題の解決に必要な場を次々と立ち上げてきました。企業になぞらえるならば、問題のある部署に放り込まれ、解決の基盤をつくる人です。“個の強みを最大化する”ことは、確実にチームを強くします。立ち上げる強みと、それを維持・運営する強みは異なりますし、企業内にも“立ち上げ屋”や“問題解決型リーダー”は昔からいたはずです。課題山積の今こそ、それを1つの職務・職責として確立すれば、そこで力を発揮したい人が必ず出てくるでしょう。 あるいは、湯浅さんのような人が組織を超えて活動し、企業とコラボレートすることも、今後はあり得ると思います。プロジェクト型のリーダーは、組織のなかの人でなくてもいい。何かを生む、何かを形にするためのリーダーは専門職。リーダーを中で育てることだけでなく、外と提携することも真剣に考えなければ、素早く、成果を出せません。これはサッカーや野球、ラグビーの監督やコーチを国内外の他チームから招聘するのと似た発想です。 また、「つながりの作法」という話も印象的でした。企業内でも、とても重要です。変革しようとするとき、会社や部署にはダメなしきたり、文化が残っている場合があります。ただ、すべてを頭から否定すると、そこに慣れ親しんできた人は、自分自身を否定されたような気持ちになる。問題を解決するのは、人です。人に動いてもらうには、まず、話を聴く。そして、こちらの価値観を押し付けるのではなく、どこがダメなのかを一緒に考える。そんなスタンスが求められます。最初はうまくいかなかった湯浅さんが、場づくりをするなかでスタンスを変えていった、というエピソードが、つながりの作法の重要性を物語っていると思います。 そんな湯浅さんに、社会活動のモチベーションを問うと、「面白いから」と言います。使命感ではなく、です。人はある組織で認められると心地いい。でも、それを捨ててどんどん次に行きます。そのタフさは、「面白さ」が原点にあるようです。成果を出す人は、楽しんでやっている。それも、私たちの大きな学びではないでしょうか。 Nakatake Ryuji_1993年早稲田大学人間科学部入学。4年時にラグビー蹴球部の主将を務め、全国大学選手権準優勝。97年卒業後、単身渡英。レスター大学大学院社会学修士課程修了。2001年三菱総合研究所入社。2006年早稲田大学ラグビー蹴球部監督に就任。2007年度から2年連続で、全国大学選手権制覇。2010年2月退任。同年4月、日本ラグビーフットボール協会コーチングディレクターに就任し、指導者の育成、一貫指導体制の構築に努める。2012年度および2014年度からラグビーU20日本代表監督を兼任。主な著書に『判断と決断』(東洋経済新報社)、『人を育てる期待のかけ方』(ディスカヴァー・トゥエンティワ ン)、『リーダーシップからフォロワーシップへ』(阪急コミュニケーションズ)、『挫折と挑戦』(PHP研究所)、『部下を育てるリーダーのレトリック』(日経BP社)など多数。日本におけるフォロワーシップ論の提唱者の1人。 *元記事は以下のリンクから読めます。 http://www.works-i.com/publication/works/works-web-special/nextage/湯浅-誠氏
(記事全文) アベノミクスの成果の一つに、雇用の増加が挙がる。だが増えているのは非正規雇用だけで、正規雇用は減っている。経営者の判断一つで首を切られてしまう非正規雇用で働く人たちは、先行きの見通せない不安がつきまとう。「企業ばかりでなく、働く人の立場を重視した政策を実行してほしい」と、衆院選の行方を見守っている。 (小松田健一) 浜元盛博(もりひろ)さん(36)=千葉県浦安市=は今年二月末、一通の手紙を受け取った。「契約が三月末で終了する」とあった。新たな契約の打診はなかった。事実上の解雇通告だった。 雇用契約を結んだイベント会社を通じ、二〇〇五年から同市の東京ディズニーシー(TDS)のショーに出演していた。衣装に身を包み主役を盛り上げる「パフォーマー」が役回り。契約は一年単位だった。「更新してもらえるだろうか」と毎年、感じていた不安が現実になった。 非正規雇用の仲間と結成した労組を通じ、東京都労働委員会に不当労働行為の救済を申し立て、イベント会社側と和解が成立したものの納得できない自分がいた。「再び舞台に立ちたい」とTDSの運営会社「オリエンタルランド」に、直接雇用を求めて団体交渉を申し込んだが、拒否された。 同社は取材に「弊社との間に雇用関係はなく、労働組合法の定める使用者には当たらないことから、交渉に応じる義務はないものと考えている」とコメントした。 浜元さんは今もアルバイトでしのぐ。「首切りが当たり前の社会にしたくない」。だが現実は、浜元さんの願いとは逆方向に進んでいる。 安倍政権が発足して二年。雇用は百二十五万人増えた。だが内訳をみると、正規労働者は四十二万人減で、より解雇しやすい派遣などの非正規労働者が百六十七万人増だった。 「非正規雇用が際限なく広がってしまう」。浜元さんも加入する労組「なのはなユニオン」(同県船橋市)委員長の鴨桃代さん(66)は今の流れを心配する。 雇用を支える中小企業の足元が揺らいでいる中、経営者の厳しさは、比較的安定しているとされてきた正社員にも向かう。 今年八月、鴨さんは千葉県内にある中小企業との団体交渉に立ち会った。手当の一方的カットに抗議する社員に対し、経営側が「彼が毎月二十五万円のコストをドブに流している」と発言した。「人間をコストと言い切るなんて…」。鴨さんはあぜんとした。 「政治が今やるべきことは、雇用安定と賃金の底上げだ。そうしなければ、社会を支える基盤が崩れてしまう」 *元記事は以下のリンクから読めます。 http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014121302000250.html