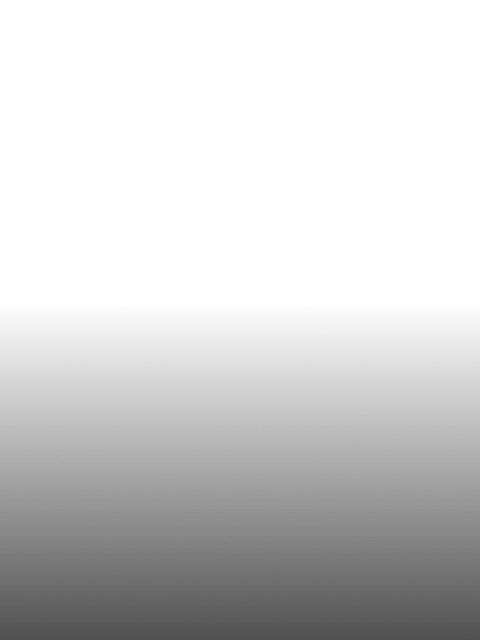利用条件
- チャンネルの購読はのに限られます
- チャンネルの購読はに限られます
- チャンネルの購読はに限られます
- チャンネルの購読はに限られます
- チャンネルの閲覧には新しい働き方会議へのアカウント登録/ログインが必要です
注意事項
- 購読ライセンスの期限を超えると、チャンネルを閲覧できません。購読ライセンスを新たにご購入ください
- 一度ご購入された購読ライセンスの返金はできません
これまでのご利用、誠にありがとうございました。


今月のGuest 未来の出版業界を牽引する 佐渡島庸平氏 佐渡島庸平氏は、講談社勤務時代、『ドラゴン桜』『宇宙兄弟』などの大ヒット漫画を世に出した。テレビアニメ化、映画化によって、それらの作品はさらに多くの人の心を震わせた。2012年10月に講談社を退職、コルクの設立に至る。同社は小山宙哉氏、三田紀房氏など人気作家を擁する作家エージェント会社だが、目指す先はコンテンツ業界の変革にある。どのような変革か。その発想を生んだ佐渡島氏とは、どのような人物か。中竹竜二氏が話を聞いた。 佐渡島庸平氏 Sadoshima Yohei_2002年講談社入社。『バガボンド』(井上雄彦)、『ドラゴン桜』(三田紀房)、『働きマン』(安野モヨコ)、『宇宙兄弟』(小山宙哉)などの編集を担当。2012年に講談社を退社し、コルクを設立。 ■「偉くなったらやる」は言い訳にすぎない 中竹 佐渡島さんは、講談社で次々とヒット作を出していらっしゃいます。外から見れば非常に充実していたように見えますが、なぜ退職したのですか。 佐渡島 決めたのは、『宇宙兄弟』の実写映画の仕事を一通り終えたすぐ後でした。この作品を世に売り出していくために、関連本を作って、映画、アニメを制作して、イベントを仕込んで、と、やっているうちに半年間休みなし(笑)。宣伝などの忙しさのピークが終わってほっとして2日間考えて、「ああ、辞めよう」と思いました。 理由はいくつかあります。1つは、そこまでやって、僕の想定よりも『宇宙兄弟』が売れなかったこと。あれこれ手を尽くしても、簡単に本が売れない。時代の変化をリアルに感じました。 そのときふと思い出したのは、堀江貴文さんにずっと前に言われた言葉でした。「今までは雑誌や本がたくさん出ていたから、白紙を埋めるために編集者が作家のもとに依頼に行った。今後はWebを含めて有象無象、作家が増えて、編集者より多くなる。だから、作家が優秀な編集者に編集してくれと依頼に来るようになる。つまり、作家エージェントの時代がやってくるから、早く辞めて、そうしたほうがいい」と。当時、僕は講談社が好きだったし、やりたいことができて自由。給料もいい。だから聞き流していたんですが、そのときはじめて「辞める」という選択肢と向き合いました。 中竹 「出版社」というモデルの枠から出ることを真剣に検討し始めた、ということですね。 佐渡島 そして、ちょうどその半年前、僕の友達が癌で亡くなってしまった。再々発で亡くなったのですが、再発後、一度回復したとき、彼が言ったことは「仕事がしたい」でした。「元気になって遊びたい」ではなく。 そのとき僕が気づいたことは、僕自身がもはや仕事を楽しんでいない、ということでした。たとえば世間的にはなんら問題ない企画でも、講談社的にNG、とかね。「世間的に問題があるんですか?」と噛み付いても、そんなロジックは通らない。当時僕は「自分が偉くなったらやろう」と自らを言い聞かせていましたが、彼が亡くなったことで、「偉くなる前に死ぬかもしれない」と思ったんです。そのとき僕は納得できないだろうし、「偉くなったらやろう」ということが、「今、挑戦しないことの言い訳であり、自分に甘えを許しているだけ」だと気づきました。 『もしドラ』の編集者が退職してベンチャーを起業したことも、頭にあったかもしれません。 ■大企業が持つ価値が、価値創出に対する社員の意識を低減させる 中竹 佐渡島さんは、自分を取り巻くさまざまな事象をつなぐことに長けていらっしゃいますね。今の話のなかでいうと、退職を決意して新しいフィールドに出た佐渡島さんの視点から、大企業で働く人をどのように見ますか。 佐渡島 大企業は、僕はある意味すごい仕組みだと思う。たとえば講談社が今日なくなったとしたら、困る人がたくさんいる。多くの社員、作品を出している作家をはじめ、印刷会社や編集プロダクションなどの取引先はもちろん混乱をきたすし、日本の文化のありようも、数年のレベルで影響があると思う。それが大企業の強さということです。だから、そこで雇用されている人は、頑張って働いても、働かなくても自動的に毎月給料が振り込まれます。 でも、それは創業者が、「自分は何者であるか」という価値を追求し、「存在しないと困る」ということを証明しようと努力した結果なのです。あらためて大企業で働く人が気づくべきは、「存在しなければ困る」という状態でずっとあるためには、本来的にはそこで働く人たちが前に進み続けなければならないことです。そうでなければ、緩やかに死を迎えてしまうんです。 ところが、大企業のサラリーマンは、自分が価値を出さなくても給料が振り込まれるというところから社会人人生が始まっている。だから、自分が価値を出すことに対して意識が薄い。 そんな偉そうに言っている僕も、講談社時代、それなりに価値を出しているつもりでしたが、入社以来ずっと減収だった会社を僕が辞めたとたんに10年ぶりの増収増益ですよ(笑)。僕がいないほうが、講談社は儲かる(笑)。でも、コルクはそうはいかない。僕が動かなくなったら、コルクという会社の入金は止まる。今後僕は、自分が自分として、そして、コルクという会社がなくなったら困る、という存在になるために活躍していかなければならないんです。 ■ 仕事を「自分ごと」化させるための「独立自由」という仕組み 中竹 大きな会社になればなるほど、そういう意識を持たせるマネジメントは難しいです。 佐渡島 どれだけ仕事を「自分ごと」化させるかがカギになります。小さな子会社をたくさん作って、若手を抜擢して社長にする仕組みを持っている会社がありますが、これは1つの方法ですね。ただ、これは会社がかなりの勢いで成長を続けないと維持できないモデルです。将来失敗するかもしれないことをやらない、という理由はないけれど、僕は違う仕組みを考えたい。 中竹 コルクで、「自分ごと」にする仕組みを考えているんですか。 佐渡島 1つは「独立自由」。社員が作家と懇意になって会社を作るならば、すぐに辞められる仕組みなんです。 中竹 それは、大胆ですね。利益の源泉である作家を奪われるうえに、競合が増えるわけですから。 佐渡島 競合が増えたほうがいいんです。日本に作家エージェント会社は、親族がやっている以外はコルクくらいしかありません。その状態だと、1つの産業として確立していないから、編集プロダクションと区別してもらえない。競合が増えて、僕らに編集者としての実力があれば、より高い値段がつくんです。だから、作家エージェントだらけになってほしい。 実際に、今、弁護士と話して、作家エージェントのあり方というか、立ち居振る舞いというか、理想的なルールをネットに公開して、多くの人が参入できるようにしようと思っているんです。 中竹 つまり、オープンソースということですか。 佐渡島 より実力があれば利益が増える。そういう状況になれば、実力を付けなければならないように追い込まれ、努力し続ける。組織が大きくなって誰かが独立すれば、またライバルが出てきて競って。そんな緊張感があってこそ、コルクが「存在し続けないと困る会社」になり得ると思います。 ■ 「後払い」から「前払い」へ課金システムを変えていく 中竹 かなりの「逆境マニア」ですね(笑)。普通は独占したほうが得と思うのではないでしょうか。 佐渡島 どんな視点でものを見るかだと思います。出版業界の市場規模が1兆7000億円、そして映画業界は2000億円といわれています。トヨタ自動車の売り上げが1社で20兆円超だと考えると、エンターテイメントはほんの小さな業界。でも、本当に小さいのか。多くの人はそう考えていません。それは、人の心に残るからでしょう。ただし、現在の出版業界を含めたエンタテインメントビジネスのモデルではこれ以上大きくならないし、作家も、そこに携わる人もハッピーにならない。それを大きく変えていこうというのが、本当の目的なんです。 中竹 どんなモデルを目指しているんですか。 佐渡島 今、大きな時代の変革期であることは言うまでもありません。「ものが売れなくなった」と先進国で言われて久しく、「いいものを作らなければ売れない」と多くの人が口にします。でも、実態は、「いいものを作っても売れない」時代なのです。すると、何がものを買う基準になるのか。それは、心理的に満足できるかどうか。満足したものにしか金を払わないということは、課金タイミングが「前払い」から「後払い」に変わっていくということであり、いいものを作っていけばいくほど、後払いのほうがより儲かる。ゲームをハードで売る会社よりも、ソーシャルゲームを展開する会社のほうが圧倒的に儲かっているのがいい例です。前払いモデルは、課金できるタイミングは一度だけで、しかも定額。しかし、ソーシャルゲームは、人の満足度曲線が上がっていけばいくほど、時間×金額の積分で、お金がきちんと取れるんです。満足度の超高い人がお金を払う仕組みは、理にかなっていますよね。 僕は、作家が作るコンテンツにもそれを適用できるように、業界を変化させていきたいと思っている。それが僕の挑戦であり、中竹さんの言う「逆境」に身を投じる1つの理由だと思います。 中竹 1社だけではなく、業界全体のルールを変えていこう、と。 佐渡島 そうです。音楽コンテンツはITを通じて配信されるようになりましたが、そのルールは音楽やミュージシャンのことをよく知る音楽業界ではなく、米国のIT業界によって作られました。だから、結果的に新人ミュージシャンが苦しむなど、ミュージシャンにとっては厳しいモデルが作られてしまいました。 米国の場合、ミュージシャンが多くいるニューヨークやロサンゼルスと、ITの集積地であるシリコンバレーが遠く離れている。それが1つの原因だったのかな、と。ところが日本は東京一極集中型で、東京のなかにIT企業も出版社などエンタメ業界もある。僕らはIT企業よりは作家の気持ちがわかりますから、僕らがITを学べば、優れたコンテンツが日本発で生まれやすくなります。日本でITとコンテンツが結びつく新しい仕組みを作ってしまうと、それが世界共通になって、世界中のコンテンツのあり方を変えていく可能性があるんです。 どんな仕組みがいいのか。それは僕が見つけてもいいし、僕に刺激を受けたライバルが見つけてもいい。とにかく、日本で生み出したい。そんな思いがあります。 ■ 会社の規模は、経営者が恐怖を乗り越えた数に比例する 中竹 逆境に身を置く理由は、ほかにもあるんですか。先ほど、「1つの理由は」とおっしゃった。 佐渡島 もう1つは、精神的にストレスがあったほうが自分にとっていいことを体験的に知っているからです。中学時代に親の仕事の都合で南アフリカ共和国に滞在したとき、大変な思いもしたんですが、後から振り返ると僕にとって貴重な経験でした。だから、2つの道があるなら、精神的にストレスがあるほうを選びます(笑)。 中竹 会社の経営においても、ストレスが多いほうがいい方向に進むだろうと思っている。 佐渡島 経営者が恐怖をいくつ乗り越えたかが、会社の規模を決めているというのが僕の持論です。ゼロから会社を立ち上げたときには、1億の投資は怖くない。そもそも、ゼロだから。ところが10億の会社になると、9億になってしまうのが怖くて1億の投資ができなくなる。特に、店舗を増やすというような現在の延長線上にあってほぼ確実にお金を生み出す投資ではなく、新しい挑戦のための投資をする恐怖を乗り越えられる経営者はほとんどいない。そういう意味で、ソフトバンクの孫正義さんやアマゾン・ドット・コムのジェフリー・ベゾスさんはすごい経営者です。 サラリーマンだった僕は、まず、そのポジションを捨てるという恐怖を乗り越えました。先に言ったように業界のルールを変えていこうとするならば、これからはもっと多くの恐怖を乗り越えていかなければなりません。孫さんやベゾスさんに恐怖心がないかというと、そうではないと思う。恐怖心のコントロール術に長けているのではないでしょうか。 ■ 緊張感と懐の深さが両立する組織を作るという挑戦 中竹 この連載のテーマは、「次世代のチーム」づくりです。経営者だけでなく、チームに参加する人全体が、恐怖心のコントロール術を身につけ、恐怖を乗り越えていく必要があると思いますか。 佐渡島 もちろん、経営陣はそうあるべきだし、コルクでは彼らと恐怖心の共有をしようとしています。以前は新卒の社員にもしていたんですが、それでは負担が重すぎることもわかりました。思い返せば、僕だって新卒のころは、ぜんぜんダメだったんです。何をするにも先輩の指示を仰いで、失敗もして。人には段階というものがありますから。 中竹 段階を踏んだとしても、コルクが存在しなくては困る会社であり続けるために、価値を出せる人材に育つかどうかを見極めることはできますか。 佐渡島 作家よりも社員のほうが見極めは難しいです。どんな仕事も才能と努力の掛け合わせ。作家はいい作品にするという同じ目標を目指して一緒に仕事をしますから、どちらも見えやすい。でも、社員とは作家ほど一緒に仕事をする機会はありません。優秀な人材でも、努力を続けられるかどうかはそう簡単にわからない。どんなトラブルでも、逃げずに向き合えるかどうか、ですね。 中竹 すごく緊張感のある組織ですね。 佐渡島 実は、そこもチャレンジです。緊張感は持っていたいが、懐も深くありたい。人にはライフステージというものがあって、育児や病気、親の介護などで仕事を緩やかにしなければならない時期もある。そういう人の人生を否定してはならない。本当は、社員自らの宣言によって、メーカー的な安定型給与体系、インセンティブ型給与体系など、いろんな意味で社員の選択肢が多い会社にしたい。ここは法律との絡みもあって、試行錯誤しているところです。 ◇ 学ぶことをやめたら、リーダーをやめなければならない 中竹竜二氏 日本ラグビーフットボール協会 コーチングディレクター 「競合が増えたほうがいい」という言葉に、とても驚かされました。それは決して強がりではないことは、インタビューを読んでいただければわかると思います。彼のこうした、常人を超えた発想はどこからやってくるのでしょうか。私はそれは、彼自身を取り巻く、あらゆる事象から学ぼうとする力から生まれるのだと思います。 「学ぶことをやめたら、教えることをやめなければならない」。これはサッカー・フランス代表元監督のロジェ・ルメール氏の有名な言葉です。チームを引っ張るリーダーは、類いまれなる学び手でなければなりません。特に、激変の時代こそ、です。変化を敏感にとらえ、それに対応するには、過去の成功体験をゼロリセットしなければなりません。 佐渡島氏のキャリアは、まさにそれを体現してきた軌跡です。入社当時、常に先輩の指示を仰がなければならず、自由度が低かった。この状況を変えるには、新連載を立ち上げるしかないと考えた。そして新連載を立ち上げたら、今度は「好きな作品しか担当したくない」と思い、新連載をヒットさせてそれを実現した。その作品が『ドラゴン桜』だといいます。その後も、部署を超えて社内のさまざまな仕事を担当できるようにするため、そして、やりたいと思ったプロモーション施策を全部実現するため、と、次へ次へと進んでいきます。その度に、過去の成功に安住せず、未来を見て、人や本、経験に向き合って、新しい学びを得ていくのです。 「学ぶことをやめない」佐渡島さんの周りには、実に面白いメンバーが集まっています。コルクを設立したとき、彼が担当していた作家たちが、彼の会社と契約を結びました。また、カリスマ編集者、カリスマライターが集まり、彼とともにコンテンツを生み出す次世代モデルづくりに力を尽くしています。 リーダー育成にはさまざまな要素がありますが、「学び続けよう」という発信が、まだまだ多くの企業に欠けています。同時に、佐渡島さんが歩いてきた軌跡のように、過去の成功体験をゼロリセットするような経験を積ませる仕掛けをしていく必要があるのではないでしょうか。 Nakatake Ryuji_1993年早稲田大学人間科学部入学。4年時にラグビー蹴球部の主将を務め、全国大学選手権準優勝。97年卒業後、単身渡英。レスタ―大学大学院社会学修士課程修了。2001年三菱総合研究所入社。2006年早稲田大学ラグビー蹴球部監督に就任。2007年度から2年連続で、全国大学選手権制覇。2010年2月退任。同年4月、日本ラグビーフットボール協会コーチングディレクターに就任し、指導者の育成、一貫指導体制構築に努める。2012年度はラグビーU20日本代表監督を兼任。主な著書に『判断と決断』(東洋経済新報社)、『人を育てる期待のかけ方』(ディスカヴァー・トゥエンティワ ン)、『リーダーシップからフォロワーシップへ』(阪急コミュニケーションズ)、『挫折と挑戦』(PHP研究所)、『部下を育てるリーダーのレトリック』(日経BP社)など多数。日本におけるフォロワーシップ論の提唱者の1人。 Text=入倉由理子 Photo=刑部友康 *元記事は以下のリンクから読めます。 http://www.works-i.com/publication/works/works-web-special/nextage/佐渡島庸平氏 (コメント) 少しサイト趣旨と外れるかなとも思ったのですが、仕事観や起業を考える上で参考になると思うのでアップしました。彼の試みは昨日放送されたNHK「プロフェッショナル仕事の流儀」でも特集されていました。興味ある方はそちらもご覧になるといいと思います。 http://www.youtube.com/watch?v=msvJmlSM2dY *おそらく動画は短期間で削除されるものと思うので気になる方はお早めに。