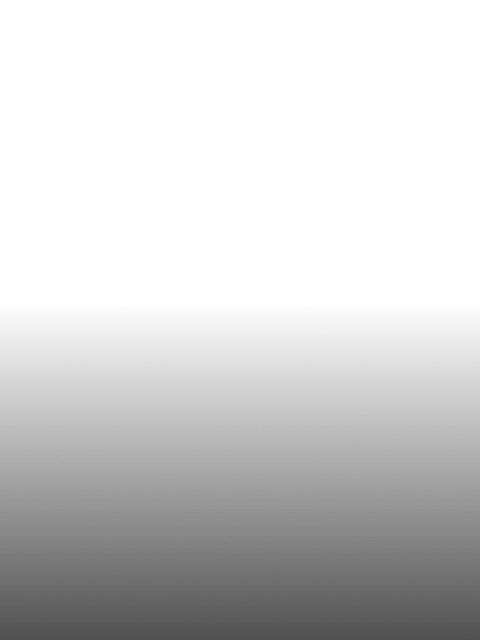利用条件
- チャンネルの購読はのに限られます
- チャンネルの購読はに限られます
- チャンネルの購読はに限られます
- チャンネルの購読はに限られます
- チャンネルの閲覧には新しい働き方会議へのアカウント登録/ログインが必要です
注意事項
- 購読ライセンスの期限を超えると、チャンネルを閲覧できません。購読ライセンスを新たにご購入ください
- 一度ご購入された購読ライセンスの返金はできません
これまでのご利用、誠にありがとうございました。
先ごろ、40代後半仲間と、チャットでちょっとしたディスカッション。 そのテーマは実にシンプル。 「仕事、働くってどういうこと?」 お金をもらうために、する仕事は苦しいもの。それをガマンして行うからこそお金がもらえるのだ。 やりがい、とか、好きなことを追い求めていたら、ずっと仕事につけない可能性も。 「わたし、これやりたいんです!」という、プッシュ型求職活動より「私が出来るのはこれとこれ。こんな私でよければ使ってください」というプル型求職活動のほうが、後のちうまく行くケースが。 仕事には「なくてはならない」が必ずつきまとう。いわく、その仕事になくてはならない人。その人にとってなくてはならない仕事。 主婦はどうなのだろう? なくてはならない人が、行う労働だか、報酬が発生しない分、「仕事」といえるのだろうか? では、誰かに感謝される、とか社会貢献という視点で考えたら? 誰かに感謝されると嬉しい。その喜びをさらに創出したくなり、より良い成果を上げるためにがんばるし、その過程で自身が成長する。 こんなのが、働く、の理想なのでは。 いやいやそれならボランティアと同じ。無報酬でも仕事といえるのか? などなど。 エンドレスループにはまりつつあるディスカッションとなりました。 皆さんはどうお考えでしょうか?


ハローライフの目的は、さまざまな環境にいる人、 多様な価値観を持つ人と人とがお互いに学びの場を持ちながら、 笑顔と活力を交換し、結果、しあわせを感じながら働く人が増えること。 100%民間の自由な発想で ”この時代の” ”これからの時代の” 働き方の新しいスタンダードを創るチャレンジが始まろうとしています。 「働き方の新しいスタンダードを創る・・・」
いつも「新しい働き方会議」をご愛読いただき、ありがとうございます。 5月中旬まで本格的に多忙になるので、1ヶ月ほど更新を中断します。 5月下旬〜6月頃には再開できると思います。 更新を楽しみにされていた方には大変申し訳ないのですが、何卒宜しくお願いします。